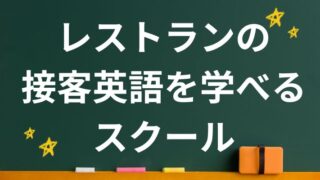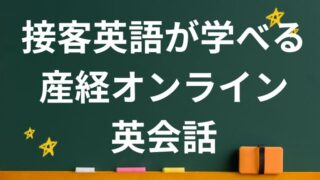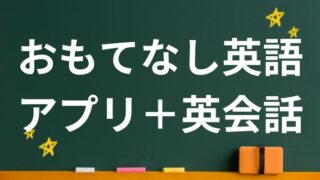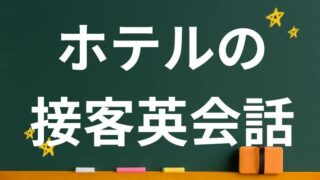新型コロナウイルスはツーリズム産業、特に、インバウンドに大きな打撃を与えました。
観光公害が起こるほどに活況を帯びていたインバウンド・ビジネスはアフター・コロナ時代へ向けた新しい指針が求められています。
ここではアフターコロナに向けて、インバウンドに関するおすすめの書籍をご紹介します。
インバウンド・ルネッサンス 日本再生
最もおすすめなのがこちらの「インバウンド・ルネッサンス 日本再生」です。
2021年11月に出版されたばかりで、早稲田大学の教授が執筆しています。
アフターコロナのインバウンドの在り方にとても参考になる本で、サステナブルなインバウンド・ビジネス戦略について解説しています。
本の紹介には以下のように書かれています。
「アフターコロナは、通常時では難しい「パラダイムシフト」が実現できる可能性が大きく、これを好機と捉え、実際に動くことができる人・組織・ビジネスに勝機がある。人の移動が制限されることにより、幸か不幸か、これまでの訪日客の増大だけを頼りにしたやり方から、いかにリピーターを増やすか、富裕層をつかむかなどという、まさに「戦略」が求められる局面を迎えているのだ」
つまり、いかにリピータを増やし、どのように富裕層をつかむかというについて解説してます。
特に、サステナブルに発展する「インバウンド・アウトバウンド・ループ(IOL)」という独自のフレームワークを提示を提示しており、以下の6つのループを提示しています。
- 非観光事業者・日本の文化等を観光資源化
- 観光資源化する際に経験・体験価値化しその付加価値を高める、
- その価値を展開するために地域内・地域間連携を促進する、
- 付加価値を高価格に転嫁することでインバウンドから得られる収益を持続的に最大化
- 効率的に越境eコマースなどを活用した海外販売につなげる
- 再度インバウンドに向かうというループとして提唱。
具体的には以下のような内容が学べます。
持続可能な成長・発展戦略モデル:インバウンド・アウトバウンド・ループ(IOL)
- インバウンド・ビジネスにおける日本の現状
- 「持続可能な観光立国日本」とインバウンド・アウトバウンド・ループ(IOL)
- 日本におけるインバウンド・アウトバウンド循環の現状
- 新潟県(燕三条地域)の事例
- 北海道の事例
- 富山県の事例
- 岡山県(倉敷市)の事例
- 瀬戸内(瀬戸内しまなみ海道地域)の事例
- 3つのカギとなる手法――経験価値・地方連携・高付加価値の価値転嫁
アフターコロナ時代の「観光立国日本」の重要テーマ
- 需要創造のマーケティング
- 日本のおけるガストロノミーツーリズムの可能性と課題
- 富裕層&ラグジュアリーマスビジネス
- 日本へ向けたメッセージ
持続可能なインバウンド・ツーリズムに向けた人材育成
- 持続可能なインバウンド・ツーリズムのリーダー育成に向けて
富士箱根ゲストハウスの外国人宿泊客はなぜリピーターになるのか?
ちょっと古い本ですが、「富士箱根ゲストハウスの外国人宿泊客はなぜリピーターになるのか?」もインバウンドに参考になる本です。
富士箱根ゲストハウスは、箱根仙石原に1984年にオープンした小さなゲストハウスです。
箱根・仙石原にある「富士箱根ゲストハウス」は現在のようにインバウンドが注目されるずっと前から外国人旅行客を受け入れ、外国人旅行客が宿泊客の大半を占めています。
また、「トリップアドバイザー」で「エクセレント認証」を5年連続で獲得した施設として「殿堂入り」を果たしており、長年にわたり外国人旅行客を受け入れてきた実績が評価され、ホスピタリティー分野における世界的権威の米国コーネル大学からアジアにおける「ベスト・プラクティス・チャンピオン」に選ばれています。
客層を見ると、およそ欧米豪から六割、アジアから三割で日本人は全体の一割程度です。
富士箱根ゲストハウスは、和室15室からなり、一泊大人1人5500円から利用が可能です。
富士箱根ゲストハウスのホームページを見るとわかりますが、お世辞にも立派な設備や部屋を提供しているわけではありません。
富士箱根ゲストハウスは、土地柄、館内のお風呂はすべて温泉で、露天風呂もありますが、民家を増改築した建物のため外観は平凡で、他にも特に立派な設備や部屋、食事を提供しているわけではありません。
しかし、富士箱根ゲストハウスは連日(コロナ前)、世界各地からやってきた旅行客でにぎわっています。
1984年の創業以来、32年間で75ヵ国15万人を超える外国人旅行客が訪れており、宿泊客の中にはリピーターも数多くいます。
簡単に「富士箱根ゲストハウスの外国人宿泊客はなぜリピーターになるのか?」を要約します。
富士箱根ゲストハウスの特徴の一つとして、日本の生活文化が体験できるということです。
「富士箱根ゲストの和室は、畳敷きに襖と障子戸のついた古典的な和室空間で、夜は布団を敷いて浴衣で休みます。日本人にとっては何の変哲もない部屋ですが、外国人の目には、日本の生活文化を垣間見ることのできる、貴重な空間に映るようです」とあります。
このように外国人旅行客にとって、日本人の普段の生活が非常に貴重であり、日本人にとっては、なんでもない風景や音も外国人旅行客には貴重であり、非常に関心を寄せているため、あえて、日常の生活を体験させてあげるということです。
つまり「ありのままの日本」を紹介しているのです。
富士箱根ゲストハウスの客室は畳、襖、障子がある典型的な和室になっており、部屋の窓からは竹林が見えたり、川のせせらぎや鳥のさえずりが聴こえたりします。
そのような空間で、浴衣を着て布団を敷いて寝ることや、温泉・露天風呂に入ることは、普段はパジャマを着てベッドで寝たり、普段はお湯を溜めたお風呂に使っていたりする外国人にとって、日本の生活文化を体験できる貴重な機会なのです。
第二の特徴としてホームステイのようなもてなしが体験できるということです。
筆者の高橋さんは「富士箱根ゲストハウスが目指す「もてなしの心」とは、「外国人を枠にはめず、こちらの価値観を押しつけず、違いは違いとして受け止めて、柔軟な心で相手の立場を思いやり、尊重すること」(p.61)と書いており、
高橋さんは30年ほど前にアメリカにホームステイをした経験があり、そこでの経験を通して、「その国のことは、家庭に入らなければ本当のことはわからない」ということを実感したということです。
そこで、富士箱根ゲストハウスでは外国人旅行者のもてなしを「友人として迎え、人としてお世話すること」と捉えているそうです。
これは言葉をかえれば「お客様扱いしない、緊張させないもてなし」ということともいえます。
富士箱根ゲストハウス代表の高橋さんは、ゲストハウスを始める前に長い間、国際教育や国際交流の仕事に従事していたため、ゲストハウスを始めた理由は、外国人をもてなしたいということではじめたといいます。
また、高橋さんがアメリカでホームステイを体験したことがあり、そのとき、体験した人の心を尊重してくれるホストファミリーのもてなしに触れたということで、それが原体験になっているそうです。
第3の特徴として、富士箱根ゲストハウスには、国際交流ラウンジと呼ばれる20畳ほどの共有スペースがあります。
そこは、誰でも自由に出入りすることができ、楽器なども置かれています。
旅行客同士が、お互いで交流を図りコミュニケーションを取り、時には、楽器を演奏し、みんなで歌い合ったりしているそうです。
富士箱根ゲストハウスに泊まりたい方はこちらから。
観光再生:サステナブルな地域をつくる28のキーワード
「観光再生:サステナブルな地域をつくる28のキーワード」は2020年11月出版の書籍で、インバウンド観光に特化したサイト「やまとごころ.jp」を運営している村山慶輔さんの著書です。
以下のような内容が学べます。
第1章観光再生に欠かせない「サステナブル」という視点
- サステナブル・ツーリズム
- リジェネラティブ・トラベル
- 地域教育とシビックプライド
- コミュニティ・ツーリズム
- 観光貢献度の可視化
- 量から質へ(発想の転換)
- BCPの策定
第2章「新技術」でネクスト・ステップへ進む
- マイクロモビリティ
- 観光型MaaS
- DX(デジタルトランスフォーメーション)
- スマートツーリズム
- バーチャルツーリズム
- ライブコマース
- AI・ロボット/非接触型機器
第3章観光の新たな「トレンド」を捉え、対応する
- アフターインスタ映え
- 食の多様化
- アドベンチャー・ツーリズム
- ロングステイヤー/ワーケーション
- レスポンシブル・ツーリズム
第4章「新戦略」で未来のニーズを先取りする
- 高付加価値化
- 富裕層(ラグジュアリー)マーケット
- ニューマーケットの開拓
- 観光CRM
- リスク分散/事業の多角化
第5章地域を支える「人」を育てる/呼び込む
- 人材の確保・育成
- サバティカル制度
- ダイバーシティ
- 関係人口の創出
なお、「観光再生:サステナブルな地域をつくる28のキーワード」はアマゾンのaudibleで無料体験で無料で聞けます。(無料体験終了後、退会しても聞き続けるこができます)
audibleの無料体験はこちら>>>audible版
山奥の小さな旅館が連日外国人客で満室になる理由
世界最大旅行サイトである「トリップ・アドバイザー」宿泊施設満足度ランキング全国3位に,「外国人に人気の日本の旅館2016」で10位にランクインした大分県の湯平温泉の山城屋の事例です。
山城屋の成功した最も大きな要因は、地元の留学生をうまく活用して、徹底して不安を安心感に変えるサービスを行っています。
山城屋の詳細は山城屋がインバウンドで成功した理由をご覧ください。
インバウンド再生: コロナ後への観光政策をイタリアと京都から考える
書いている方が研究者なので、かなり学術書的な内容ですが、信頼できるデータに基づいており、読み応えがあります。
コロナ後の観光政策を京都とイタリアを例に提案しています。
こんなことが学べます。
- コロナ直前、日本で起こっていたこと
- ヨーロッパ観光産業の四つの発展段階
- 団体旅行の誕生から個人旅行への転換
- 地方の小都市の観光公害と交通まちづくり
- 観光を生かしたイタリアの稼ぎ方―ホストとゲストの出会いが生んだスモールビジネス
- 女性が変えた京都の観光政策―町家・町並みを育てたアウトバウンド経験
- 観光都市ではなく文化・芸術都市を目指す
- アウトバウンドとインバウンドが生んだ四つのシフト
- コロナ後に向けた地方都市の観光再生
- 観光公害とコロナ・ショックから何を学ぶべきか
観光立国政策と観光都市京都
2020年に出版された本です。
京都に焦点をあててオーバーツーリズムや持続可能な観光について考え、アフターコロナのインバウンドの在り方を提言している本です。
京都のインバウンドについて徹底して学びたい方には最適な本です。
以下のような内容が学べます。
第1章 京都観光の理念と観光立国政策
- 「インバウンド旋風が吹き荒れている」
- 「“観光公害”はいつから始まったのか」
- 「呼び込み観光は東山区を荒廃させる」
- 「東山区のまちづくりを考える」
第2章 安倍政権、地方創生の陥穽
- 「地方創生に期待できますか」
- 「“たられば”では、人口減少に歯止めがかからない」
- 「希望から現実へ、出生率を上げるには」
- 「少子化が“国難”なら2兆円パッケージは少なすぎる
第3章 京都はスローな成熟都市
- 「京都はスローな成熟都市なのです」
- 「死亡が出生を上回る都市に未来はあるか」
- 「京都市の出生率、なぜ低い」
- 「全国最下位出生率から脱出が課題」
- 「門川市長も危機感、京都観光業の雇用実態」
第4章 民泊上陸が意味するもの
- 「民泊バブルは現代の黒船来襲なのだ」
- 「首相官邸が指揮した民泊規制改革」
- 「民泊新法のビフォーアフター」
- 「民泊新法施行でヤミ民泊はどうなる」
- 「民泊はもはや供給過剰、飽和状態なのだ」
第5章 民泊新法を巡る攻防「エアビーの身勝手な言い分」
- 「旅館業法の適用除外が眼目」
- 「規制改革会議主導の民泊導入は頓挫した」
- 「民泊新法施行半年の光と影」
- 「京都の民泊は簡易宿所に流れた」
第6章 オーバーツーリズムの危機
- 「オーバーツーリズムの危機が現実化している」
- 「“モンスター化”する観光産業をどうする」
- 「富裕層観光の表と裏」
- 「門川市政の原罪、オーバーホテル問題」
- 「京都の平成時代は“狂乱状態”で終わるのか」
- 「京都は“インバウンド総量規制”が必要だ」
第7章 京都市長選における政策転換
- 「観光政策の見直しは時代の変わり目に」
- 「次期京都市長選では観光政策が一大争点に」
- 「京都が京都でなくなる日」
- 「もうそこまで来ている、京都が京都でなくなる日」
- 「本物の観光都市、いわゆる観光都市」
- 「京都市長選を通して浮かび上がった基本問題」
第8章 京都観光の歴史的転換点
- 「絶頂からどん底へ、4期目門川市政が直面するもの」
- 「京都市政、観光立国から脱却のとき」
- 「世界はビフォーコロナからアフターコロナへ」
- 「新型コロナ危機の下で京都市基本計画、観光振興計画はどうなる」
オーバーツーリズム: 観光に消費されないまちのつくり方
以下のような内容が学べます。
オーバーツーリズムとは
- 訪日外国人観光客の急増とその背景
- オーバーツーリズムの影響
- オーバーツーリズムのタイプと対策
海外のオーバーツーリズム
- 人気観光拠点型-スペイン・バルセロナ市など
- リゾート型-タイ・ピピレイ島など
- 稀少資源型-エクアドル・ガラパゴス諸島など
国内のオーバーツーリズム
- 人気観光拠点型-京都府京都市など
- リゾート型-沖縄県恩納村
- 稀少資源型-富士山
新たなオーバーツーリズムとその対策
- ソーシャル・メディアが生む次世代オーバーツーリズム
- ICT、AIを活用したブレークスルー
- レスポンシブル・ツーリズム(責任ある観光)
- オーバーツーリズムへの向きあい方
北海道の美瑛町や鎌倉、国外ではスイス・パラオ・ヒマラヤの事例なども書いてあり、とても興味深い内容でした。
住民と自治 2020年 5月号
住民と自治 2020年 5月号がオーバーツーリズムについて特集を組みました。
その中で、新型コロナウイルスで一気に冷え込んだ、インバウンド頼みの日本の観光のあり方について問題を提起しています。
以下のような内容が学べます。
- 「観光立国」政策とオーバーツーリズム(堀田祐三子)
- 欧州諸都市のオーバーツーリズムへの取り組み(阿部大輔)
- ちぐはぐな京都市の観光政策(中林 浩)
- 奈良公園にリゾートホテルはいらない(中島 晃)
- 外需、外国依存のクルーズ船観光の危険性(池田 豊)
- 民泊法制度の現状と課題─地方自治体の独自規制に着目して─(堀田祐三子)
- 「山里ツーリズム」への模索─九州脊梁の「日本遺産」登録を見据えて(中島熙八郎)
- 新型コロナ 揺らぐ現場からの報告
- 新型コロナウイルス感染拡大を阻止するために奮闘する医療現場から(森田 進)
- 新型コロナウイルス対応を行う自治体労働者の現状(水戸川慶太)
- 一律休校がもたらしたもの(宮下直樹)
- 学童保育の現場から─不安と疑問のなかで(井上静子)
- 消費税増税と「新型コロナ危機」 中小業者の苦難打開へ(中山 眞)
- 「新型コロナウイルス」問題が広がるなかで(河村泰三)
観光のまなざしと東アジア-中国人インバウンドのジレンマ-
最後は少し変わった本です。
中国の研究者の博士論文を書籍にした本です。
中国人に立場から、中国人インバウンドについて考察しています。
「つい最近までアジアの中でも観光後進国の立場である日本は、タイやフランスなどの観光強国と比べて、外国人観光客を大量に受け入れるインフラの基盤が思っていたより脆弱である。一方、中国国民も海外観光の歴史が浅く、現在のように世界中を闊歩することが当たり前になったのもごく最近のことである。日本社会で見られるインバウンド事業の諸問題の本質は、未熟な「ゲスト」と未熟な「ホスト」が短期間で大量且頻繁に接触することによるものであると筆者は考えている。」
と記してあり、日本で生活する中国人研究者の目線から、中国人インバウンド側の状況を如実に反映し、日本人研究者が気づきにくい、ホスト側としての日本社会の様々な課題を提起しています。
以下のような内容が学べます。
- 日本の民泊政策から見る外国人観光客へのまなざし
- 名古屋城の観光の現場から見る中国人観光客へのまなざし
- 金門島の本土中国人ツアーから見る相互のまなざし
- 白川郷から見る台湾人観光客へのまなざし
- 中国大陸と台湾における日本植民地建築へのまなざし
- 日中台三地域の観光行政体制の比較
- 中国語歌詞の「旅」文化から見る観光のプラス作用
- ポストコロナのインバウンド事業観光産業
リスクに関する回避策として、地域の公民館の共同運営を提案するなど、他の書籍とはかなり異なる観点から考察しており、読み応えがありました。
まとめ
ここではアフターコロナに向けて、インバウンドに関するおすすめの書籍をご紹介しました。
アフターコロナのインバウンドのキーワードは持続可能な観光(SDGs)やオーバーツーリズムでしょう。
持続可能な観光(SDGs)については以下で解説しています。
その他のインバウンド関係の記事です。